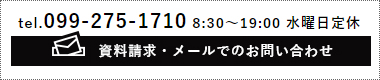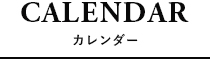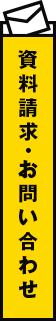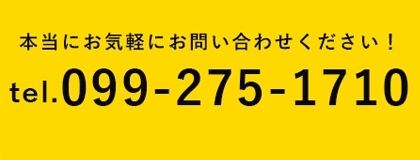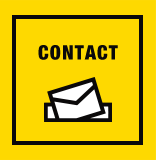2020/12/26理想の山
野に分け入り薪を拾い、山菜を摘みタケノコを掘り、子供はウベやアケビに
胸を躍らせ、時には野鳥を捕獲したりと豊かな山の姿を知っている人は
昭和35年位までに生まれた方になるでしょうか。
鹿児島市の中心街で育った方は別として、鹿児島県人の多くはこのようにして山と共に
生きていた時代を思い浮かべることができるのではないでしょうか。
多くは高齢者と呼ばれるようになりましたが。
別に郷愁に浸って昔を懐かしんでいるのではありません。
伝えたかったのは山の姿が、植生が随分と変わってしまったということです。
山を身近にして生きていかなくてもいいようになったからなのですが、
それが近年の山地災害の原因になっているように思うのです。
高速道路で熊本に向かうと、あちこちに山崩れしたあとが残っています。
いずれも戦後杉の植林された山地だと分かります。
ではなぜ杉山は崩れやすいのかということです。
それは多様な植生になっていないからだといえます。
杉山に入ると暗くて地面はむき出しになっていることが多いです。
そこに大雨が降り続きますと、保水力がないものですから一気に災害の危険性をはらむ
ようになります。人工植林されて手入れされない山は、いたるところに見かけるように
なりました。本当に危ない山の現状です。
僕の知っている健全な山は、針葉樹が中心にはありますが決してそればかりではなく、
その下に幾種類もの葉のある植物が、さらにツル物の木、実をつける木、さらに下には
カズラや地を這うような植物と多種多様な植物で共存する山の姿です。
地表には積年の落ち葉がつもり、ミミズや小さな虫が息づいているような山です。
それは山に入るとわくわくする楽しみのある山でもあります。鳥や動物に出くわし、
野ブドウや野イチゴのお目にかかれる豊かな姿です。
杉を植林するのはいいことですが、太陽の光が地表面に届くように間伐をすると、自然と
多様な動植物が寄ってくるようになります。さらに災害にも強い山になりますので安心です。